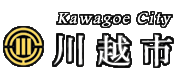高額療養費について
最終更新日:2024年2月6日
医療費の支払いが高額になった世帯の負担を軽減するため、高額療養費支給制度を実施しています。自己負担限度額を超えた額が、申請することによって支給されます。
70歳未満の方
| 区分 | 自己負担限度額(月毎) | 年間多数該当(注2) |
|---|---|---|
旧ただし書所得(注1) |
252,600円+ |
140,100円 |
旧ただし書所得600万円超 |
167,400円+ |
93,000円 |
旧ただし書所得210万円超 |
80,100円+ |
44,400円 |
| 旧ただし書所得210万円以下(エ) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯(オ) | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
(注2)年間多数該当とは、直近12カ月以内に同一世帯において、高額療養費の支給が4回以上になった場合の4回目以降のことです。
計算上の注意
- 歴月の1日から末日ごとの受診で計算します。
- 複数の医療機関にかかった場合、医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも、入院、外来と歯科については別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用でないものは対象になりません。
- 70歳未満の方は、一部負担金が21,000円を超えたものを合算対象とします。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
入院や通院で医療費が高額にかかる場合は、事前に手続きを取ることにより、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けることが出来ます。「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は保険証と一緒に医療機関に提示をすれば、窓口での支払いが限度額までとなります。
- 「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」は国民健康保険税に滞納があると交付出来ません。
- ご世帯に所得の申告のない方がいる場合は、最上位の区分(ア)とみなし適用区分を決定します。
慢性腎不全等で、人工透析を要する方の1ヶ月の自己負担限度額は、区分(ア)、(イ)の方が2万円、区分(ウ)、(エ)、(オ)の方が1万円です。
70歳以上の方
| 区分 | 外来(個人単位)の限度額(月毎) | 外来+入院(世帯単位)の限度額(月毎) | |
|---|---|---|---|
現 |
現役並み3(注2) |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント |
|
現役並み2(注2) |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント |
||
現役並み1(注2) |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント |
||
| 一般 | 18,000円 |
57,600円 |
|
低所得者2(注3) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1(注4) |
8,000円 | 15,000円 | |
(注1)年間多数該当とは直近12カ月以内に同一世帯において、外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給が4回以上になった場合の4回目以降のことです。
(注2)現役並み所得者とは、同一世帯に各種控除後の住民税課税所得が年間145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方のことです。ただし、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の収入の合計が、2人で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請することにより一般になります。また、昭和20年1月2日以降の誕生日の方がいる世帯で、旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合も一般となります。
課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いた額です。
(注3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の方です。(低所得者1以外の方)
(注4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が必要経費等を差し引いたときに0円になる方です。ただし、年金収入が80万円以下であること。
(注5)年間上限額とは、1年(8月~翌7月)の自己負担額を合算して計算する際の限度額です。一般のほか低所得者2・1だった月の外来の自己負担額も含みます。
計算上の注意
- 歴月の1日から末日ごとの受診で計算します。
- 外来分は、個人ごとに計算し、外来(個人単位)の限度額を超えた分が支給されます。
- 入院分と外来分が両方ある場合は、まず個人ごとの外来分の支給額を計算し、その後入院の一部負担金と合わせて、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた額が支給されます。
- 入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用でないものは対象になりません。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
慢性腎不全等で、人工透析を要する方の1ヶ月の自己負担限度額は、1万円です。
現役並み2、現役並み1、低所得者2、低所得者1に該当する場合、医療機関窓口での支払いを限度額までに抑えるには、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」が必要です。事前に申請をし、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受け、保険証と一緒に「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すれば、窓口での支払いが限度額までとなります。
現役並み3、一般の区分の方は、「限度額適用認定証」の交付対象ではありません。保険証をご提示いただくと、医療機関窓口での支払いが限度額までになります。
マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について
マイナンバーカードの保険証としての利用が開始されたことに伴い、専用のシステムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が原則不要になりました。(システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに掲載しています)
ただし、以下の方は医療機関等へ限度額適用認定証を提示するなどの必要があります。事前に市へ申請し、限度額適用認定証などの交付を受け、医療機関等へ提示してください。
1.システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
2.申請月以前12か月に90日を超える長期の入院をされていて、食事療養費が減額の対象になる場合
3.国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
※マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要です。
お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318