個人住民税(市民税・県民税)Q&A(令和7年度版)
このページは令和7年度を基準に作成されています。
年度の途中で引っ越した場合、住民税はどうなりますか?

Q.私は令和7年3月15日に川越市からA市に引っ越しました。令和7年度の住民税はどちらに納めるのですか。
A.川越市に納めていただきます。住民税は、その年の1月1日現在、居住していた市町村で課税されます。あなたの場合、令和7年1月1日は川越市に居住していましたので、令和7年度の住民税は川越市に納めていただくことになります。
亡くなった人の住民税はどうなりますか?

Q.私の父は令和7年2月に死亡しましたが、令和7年度の住民税の納税通知書が送られてきました。納めなければならないのですか。
A.納めていただきます。住民税は、その年の1月1日現在、市内に住んでいる人に対し、前年の所得に基づき、課税されます。したがって、令和7年1月2日以降に亡くなった人に対しては、令和7年度の住民税は課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
海外に赴任する場合、住民税はどうなりますか?

Q.私はA社に勤務し川越市の独身寮に住んでいましたが、令和6年10月から2年間の予定で海外に転勤することとなりました。令和7年度の住民税はどうなりますか。
A.あなたの場合、令和7年度の住民税は課税されません。住民税の場合、1年以上の予定で出国し、1月1日現在、国内に居住しておらず、かつ事務所、事業所または家屋敷を有しない人はその年の納税義務はないものとされています。ただし、1月1日現在、出国していても出国の期間や目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
納税通知書が2通届いたのですが、なぜですか?

Q.今年6月に納税通知書が届きましたが、9月にまた納税通知書が届きました。どうしてですか。
A.納税通知書が2通届くのは次のような理由によります。
- 本人の申告あるいは市役所の調査によって、税額が変更になった場合、あらためて納税通知書を送付します。新しく届いた納税通知書で納めてください。ただし、1月の納期以後に税額が増えた場合は、前の納税通知書の分とあわせて納めていただく場合があります。
- 年度をさかのぼって、税額が変更もしくは新規に課税になった場合、今年度分とは別に、「過年度分」として、納税通知書を送付します。納税通知書の1ページの右上に何年度に相当するかが記載されています。
源泉徴収票と税額通知書の控除額が違うのはなぜですか?

Q.会社から年末に受け取った源泉徴収票と6月に受け取った特別徴収税額通知書では所得控除の額が違いますが間違っていませんか。
A.間違いではありません。源泉徴収票は所得税の内容で、特別徴収税額通知書は住民税の内容になっています。所得税と住民税では控除額が異なります。金額が違っていても誤りではありません。なお、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除については、控除額が同じになります。
会社員も申告が必要ですか?

Q.私は会社で年末調整をしたのですが、市役所から申告書が届きました。会社員でも申告をしないといけないのですか。
A.給与支払者(会社)は、従業員の前年中の給与の支払額など一定の事項を記入した給与支払報告書を作成し、市に提出しなければなりません。これがきちんと果たされていれば、自動的に従業員本人の申告は不要となります。会社が年末調整を行っていても、給与支払報告書を提出していない場合には、従業員本人が申告するか、会社から提出してもらうか、のどちらかをしていただく必要がありますので、お勤め先にご確認ください。
なお、給与支払報告書が提出されていても、医療費控除などの年末調整で受けることのできない控除や年末調整でもれてしまった控除を受ける場合には、自分で申告をする必要があります。

Q.私は勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、住民税の場合は申告をする必要がありますか。
A.申告の必要があります。所得税では、所得の発生した時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要とされています。一方住民税では、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、必ず申告しなければなりません。
住民税は給与から差引きできますか?

Q.納税通知書が自宅に届きました。令和7年6月から会社に勤めていますが、住民税を給与から差引きすることはできますか。
A.住民税は、個人で納める方法(普通徴収)と給与から差引きして納める方法(給与特別徴収)があります。普通徴収から給与特別徴収にする場合、会社の経理担当者と市役所とで手続きをしますので、会社の経理担当者に、給与特別徴収にしたい旨をお話しください。ただし、会社によっては給与特別徴収をしない場合があります。
住民税が給与から差引きされているのに納税通知書が届いたのはなぜですか?

Q.毎月給与から住民税が差引きされているのに自宅にも納税通知書が届きました。二重に課税されていませんか。
A.前年、給与以外の他の所得がある場合、給与とその他の所得との合算の所得(総所得)に対する税額から、給与に対する税額(給与から差引き)を差し引いた分の納税通知書を本人あてに送付することがあります。この差額分は給与からあわせて引くこともできますので、希望される場合はご連絡ください。
また、公的年金を受給しており、一定の要件を満たす65歳以上の方は、公的年金の収入にかかる税額については、年金からの差引きになります。ただし、その初年度については、10月の年金支給分から差引きを開始する関係上、4月・6月・8月の年金支給分では差引きができませんので、その分は普通徴収として納付書を送付しております。なお、公的年金から差引きすべき税額については、給与からの差引きに合算できません。
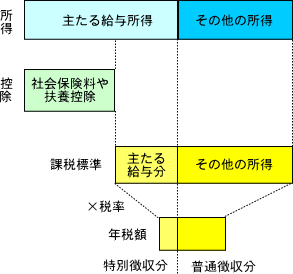
会社を退職したときの住民税はどうなりますか?

Q.私は令和7年3月に会社を退職し、退職金から残りの住民税を一括で納めました。その後は無収入ですが、令和7年度の納税通知書が自宅に届きました。なぜですか。
A.住民税は前年の所得に対し、翌年課税されます。あなたの場合、令和6年度の住民税(令和5年中の所得が対象)は退職金から一括納入済ですが、新たに令和7年度の住民税(令和6年中の所得が対象)が課税されます。今回送付した納税通知書は令和7年度分です。

Q.私は令和7年8月に会社を退職し、住民税は8月分の給与まで差引きされていました。残りの住民税はどうなりますか。
A.住民税を給与から差引きされている人は、6月から翌年5月までの12回で1年分を納めていただくことになっています。あなたの場合は8月分まで差引きが済んでいますので、残りの9月分から翌年5月分までを自分で納める必要があります。
なお、自分で納める場合の納期は全4回(6月、8月、10月、翌年1月)ですが、あなたの場合、すでに2回の納期が過ぎているので、残りの税額を二等分した納税通知書を送付します。
退職所得にかかる住民税はどのように計算しますか?

Q.私は来月、定年退職をする予定ですが、退職金にかかる住民税はどのように計算して納めるのですか。
A.退職所得にかかる住民税は、退職金が支払われる際に差引きされ、支払者(会社など)を通じ、市町村へ納入していただきます。
計算方法は下記リンク先をご覧ください。
年金受給者に住民税はかかりますか?

Q.私は会社を定年退職し、現在は年金で生活しています。年金にも住民税はかかりますか。
A.国民年金、厚生年金、企業年金、恩給などの公的年金等および生命保険契約などに基づく個人年金は「雑所得」として課税の対象になります。
ただし、遺族年金、障害年金などは課税の対象になりません。
公的年金等についての所得の算出方法は下記リンク先をご覧ください。
お年寄りの扶養はどうなりますか?

Q.私は高齢の父を扶養しています。なにか特例はありますか。
A.扶養親族が70歳以上(昭和30年1月1日以前生まれ)の場合、納税者又は納税者の配偶者の同居の直系尊属であれば45万円、そうでなければ38万円を老人扶養控除として所得金額から控除することができます。
パート収入がある場合の住民税はどうなりますか?

Q.私はサラリーマンの妻ですがパートで働いています。収入は103万円以下におさえたほうがよいと聞きますがどういうことですか。
A.パート収入は、通常、給与所得として扱います。
課税される所得は、パートの年収から給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(43万円)などの所得控除を差し引いた残額です。
パート収入以外に、営業、不動産、年金収入などがある場合は、それぞれの所得金額を算出し、その合計額で計算を行います。
注記:前年中(1月1日から12月31日)の給与所得に対して課税されます。
夫婦の一方(夫)が会社員で、もう一方(妻)がパートで働いている場合、夫婦が生計を一にしているなどの要件に当てはまれば、夫は配偶者控除(33万円)が受けられます。
また、妻のパート収入が103万円を超えていても、201.5万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
ただし、夫の給与収入が1,195万円を超える場合は、配偶者特別控除を受けることはできません。
妻のパート収入と税金及び夫の配偶者控除、配偶者特別控除の関係については、下記の表のとおりになります。
|
夫の給与収入 1,095万円以下 |
夫の給与収入 1,145万以下 |
夫の給与収入 1,195万以下 |
|
|---|---|---|---|
|
妻のパート収入 103万円以下(配偶者控除) |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
|
妻のパート収入 155万円以下(配偶者特別控除) |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
|
妻のパート収入 160万円以下(配偶者特別控除) |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
|
妻のパート収入 166.7万円以下(配偶者特別控除) |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
|
妻のパート収入 175.1万円以下(配偶者特別控除) |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
|
妻のパート収入 183.1万円以下(配偶者特別控除) |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
|
妻のパート収入 190.3万円以下(配偶者特別控除) |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
|
妻のパート収入 197.1万円以下(配偶者特別控除) |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
|
妻のパート収入 201.5万円以下(配偶者特別控除) |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
夫の給与収入が1,195万円超の場合は、配偶者特別控除は受けられません。
上記の内容については、税法の改正等により変更される場合があります。
均等割とは?
一定以上の所得のある市民の皆様に、広く均等(定額)に負担していただくものです。
市民税3,000円、県民税1,000円
所得割とは?
所得の額に応じて負担していただくもので、一般に次の計算式で算出されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等=所得割額
成人は扶養に入れられますか?

Q.私の子供は、すでに成人していますが扶養控除の対象になりますか。
A.同一生計で前年の合計所得金額が48万円以下(給与所得者の年収になおすと103万円以下)であれば年齢に関係なく扶養控除が受けられます。
アルバイトをしている子供に住民税はかかりますか?

Q.私の子供は17才でアルバイトをしています。未成年者に住民税はかかりますか。
A.未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,043,999円以下)であれば住民税はかかりません。この金額を超えると通常の税率で課税されます。
注記:未成年者は、その年の1月1日現在の状況で判定します。

Q.私の子供は21才でアルバイトをしています。学生ですが住民税はかかりますか。
A.学生の場合でも、課税の対象になります。ただし、前年の合計所得金額が75万円以下(給与所得者の年収に直すと130万円以下)であれば、勤労学生控除26万円を所得金額から差し引くことができます。
医療費の控除はどのように計算しますか?

Q.昨年、多額の医療費を支払いました。どんな控除がありますか。
A.自分や家族の医療費を支払った場合は、次の式で求めた金額を医療費控除として、所得から差し引くことができます。
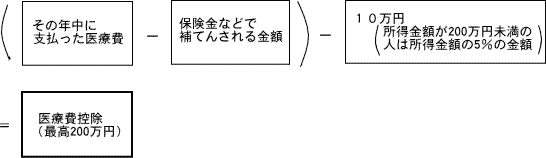
また、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(健康診断等の受診、インフルエンザワクチンの予防接種または定期接種など)を行う個人が、一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合は、次の式で求めた金額をセルフメディケーション税制による医療費控除として、所得から差し引くことができます。
注記:セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受ける受けることができません。
「一定の取組」や具体的なスイッチOTC医薬品の品目について詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
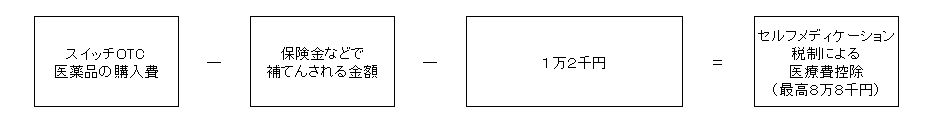

Q.私は住民税が非課税ですが、昨年、医療費がたくさんかかりました。控除を受けられますか。
A.受けられません。医療費控除は税金の控除です。したがって、税金がかかる人のみが対象です。
所得税の還付を受けたのですが、住民税の還付はありますか?

Q.私は2月に税務署で前年の所得について確定申告をして、所得税の還付を受けました。住民税の還付は受けられますか。
A.原則的に住民税は還付されません。所得税は、給与、年金などが支払われる際にその支払額に応じた税額があらかじめ差引きされます。しかし、その税額は確定したものではないので、年末調整または確定申告をすることで所得税を精算し、不足分については納付、過剰分については還付となります。
一方住民税は、確定した資料により税額を計算して納税通知書(会社から差引きされている方は税額通知書)を送付しているため還付はありません。ただし、上場株式の配当等の支払い、上場株式等の譲渡益の支払いを受けた方で、それに応じた税額が差引きされている方については、還付が発生することがあります。
障害者に特例はありますか?

Q.納税者本人や扶養親族が障害者手帳の交付を受けている場合、特例はありますか。
A.納税者本人が前年12月31日現在に障害者であり、前年の合計所得金額が135万円以下である場合、その年の住民税はかかりません。
また、納税者本人もしくは扶養親族(配偶者を含む)が障害者のときは、障害者控除として1人あたり26万円(特別障害のときは30万円)を所得金額から控除することができます。
注記:扶養親族が特別障害者で同居している場合は、さらに同居加算分として23万円を所得金額から控除することができます。
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640 ファクス番号:049-226-2540
財政部 市民税課 市民税第一担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。








