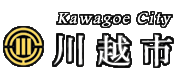固定資産税・都市計画税 税額の計算(家屋)
最終更新日:2024年4月1日
課税対象となる家屋
次の要件を満たした住宅、店舗、工場、車庫、物置等が対象です。
| 外気遮断性 | 屋根および外壁を有し、一定の空間を有していること |
|---|---|
| 土地定着性 | 土地に定着していること |
| 用途性 | 家屋が居住、作業、貯蔵等の用途に利用できる状態にあること |
- 家屋の一部が未完成であっても、家屋の使用が開始されている場合は、課税の対象となる場合があります。
- 既製品建物であっても、上記の要件を満たす場合には課税対象となります。
家屋調査
家屋を新築または増築された場合、原則として、完成(取得)した年の翌年度から固定資産税および都市計画税(市街化区域内に所在する場合)の課税対象になります。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するため、主に平面図などの資料より家屋調査を行います。
そのため、平面図などの資料のご提供や現地調査のご依頼をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。
図面による調査内容につきましては、いただいた資料から内部および外部の仕上げや建築設備等を確認させていただきます。
なお、川越市役所資産税課の職員が現地にお伺いして調査を行う場合、調査内容は図面調査時と同様であり、調査時間は30分程度(住宅100平方メートル程度の場合)となります。
家屋の評価額の算出
家屋の評価額は、総務省が定めた「固定資産評価基準」に基づき算出します。
新築・増築家屋の評価
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額
| 再建築費評点数 | 「固定資産評価基準」に基づき算出される家屋の評点数 |
|---|---|
| 経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる減価率 |
| 評点一点当たりの価額 | 点数を金額に換算するための換算率 |
新築・増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われ、平成では「3」の倍数の年度(例:平成27年度、平成30年度)で行われました。令和でも「3」の倍数の年度(例:令和3年度、令和6年度)に行われます。
評価額=基準年度の前年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率×経年減点補正率×評点一点当たりの価額
再建築費評点補正率
前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動率
令和6年度の評価替えの際に用いられた数値は「木造家屋=1.11」「非木造家屋=1.07」です。
注記:上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
課税標準額(家屋)の算出
家屋については、原則として上記評価額がそのまま課税標準額となります。
税額(家屋)の算出
固定資産税=課税標準額(評価額)×税率(1.4パーセント)
都市計画税=課税標準額(評価額)×税率(0.3パーセント)
新築住宅の減額措置
次の要件を満たす新築住宅については、新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)、家屋に係る固定資産税が2分の1に減額されます。減額の範囲は住宅部分の床面積のうち120平方メートル分までです。
面積要件
(ア)専用住宅(区分所有住宅・戸建賃貸住宅を含む)
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(イ)戸建以外の賃貸住宅(共同住宅・アパート等)
1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ウ)併用住宅
住宅部分の床面積が当該家屋の延べ床面積の2分の1以上であり、且つ、次の要件を満たすものであること
- 一般の併用住宅については、上記(ア)の要件
- 戸建以外の賃貸併用住宅については、上記(イ)の要件
認定長期優良住宅の減額措置
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅(認定を受けるには工事着工前に申請が必要)を建築された場合は、上記「新築住宅の減額措置」に替えて、新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)の減額措置を受けることができます。
なお、減額措置を受けるためには手続きが必要です。
詳しくは、下記関連情報「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度」をご参照ください。
関連情報
熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額について
お問い合わせ
財政部 資産税課 家屋担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5684(直通)
ファクス:049-226-2539