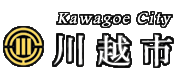市・県民税の主な税制改正について(平成30年度より適用)
最終更新日:2019年4月14日
1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
制度の概要
平成28年度税制改正で、医療費控除の特例の創設がされました。
詳しくはこちらをご覧ください。
![]() セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
一定の取組(※1)について
本特例の適用を受けるには、次のいずれかの取組を行っている必要があります。
- 予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種または定期接種)
- 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 市町村が実施するがん検診
スイッチOTC医薬品(※2)とは
スイッチOTC医薬品とは要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。対象となるスイッチOTC医薬品は、特定の成分が含まれる医薬品で、かつ指定を受けた商品です。
一部の製品については対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。また、レシート等にこの税制の対象商品である旨の記載がされています。
対象医薬品は、更新される場合があります。
申告に必要な書類について
1.健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類(下記(1)~(3)が記載されたもの)
- インフルエンザ予防接種または定期予防接種の領収書または予防接種済証
- 健康診査の領収書または結果通知表
- 定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収書または結果通知表
- 市町村のがん検診の領収書または結果通知表
(1)氏名
(2)取組を行った年
(3)当該取組に関する事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称、または当該取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
※単に保険者から補助を受けて人間ドックを受診する場合等、結果通知表に保険者や勤務先の名称についての記載がないときは、別途保険者等による取組を行った旨の証明書が必要です。
![]() 一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
2.医療品の購入の対価に係る領収書に基づいて作成した明細書(下記(1)~(4)を記載したもの)
(1)スイッチOTC医薬品を購入した薬局などの支払先の名称
(2)購入したスイッチOTC医薬品の名称
(3)スイッチOTC医薬品の購入金額
(4)保険金などで補てんされる金額
注意事項
セルフメディケーション税制は医療費の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるので、いずれか一方を選択して適用を受けることとなります。本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
また、本特例の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後納税者が更正の請求をし、または修正申告を行う場合において、従来の医療費控除への適用を変更することはできません。また、従来の医療費控除の適用を受けることを選択した場合も同様です。
2.医療費控除の提出書類の簡略化
平成28年度の税制改正で、医療費控除の提出書類の簡略化がされ、平成30年度市・県民税(平成29年分所得)から医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書の代わりとして医療費控除の明細書が必要になりました。また、医療保険者が交付する医療費通知(お知らせ)を添付することにより、明細書の記入を省略できる場合があります。
ただし、医療費の領収書は、税務署や市役所から提示を求められる場合がありますので、自宅等で5年間保存してください。
医療費の明細書について
医療費の明細書は、次の事項の記載が必要です。
(1)医療費の額
(2)診療等を受けた者の氏名
(3)診療等を行った病院、診療所その他の者の名称または氏名
(4)保険金などで補てんされる金額
医療費通知書(お知らせ)について
医療費通知書は医療保険者(注1)から交付を受けた医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などが該当します。
以下の項目を記載した医療費通知に限ります。
(1)被保険者(またはその被扶養者)の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
(5)被保険者またはその被扶養者が支払った医療費の額
(6)保険者の名称
(注1)医療保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含みます。)、国民健康保険組合、共済組合または日本私立学校振興・共済事業団、及び高齢者の医療に関する法律に規定する後期高齢者医療広域連合をいいます。
注意事項
平成28年分以前の確定申告にて医療費控除を受ける場合は、従来どおり医療費の領収書などを添付または提示してください。
おむつ代やストマ用具購入費等がある場合は、従来どおり「おむつ使用証明書」や「ストマ用装具使用証明書」等が必要です。
3.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,200万円(控除額230万円)を、平成30年度以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。
給与所得控除上限額の変更 |
平成28年分の所得税(注1) |
平成29年分以降の所得税(注2) |
|---|---|---|
上限額が適用される給与収入 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
230万円 |
220万円 |
- (注1)住民税については、平成29年度に適用
- (注2)住民税については、平成30年度以降に適用
4.配偶者控除・配偶者特別控除制度の見直し
平成29年度税制改正で、配偶者控除・配偶者特別控除制度の見直しがされ、平成31年度の市・県民税(平成30年分所得)から以下のようになります。
(1)配偶者控除・配偶者特別控除ともに納税義務者に所得制限が設けられ、納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下に引き下げられます。これを超えると控除額が所得に応じて段階的に減っていきます。
(2)配偶者控除(70歳以上の老人控除対象配偶者を除く)と同じ配偶者特別控除額が適用される配偶者の合計所得金額の上限額が90万円(給与収入155万円)に引き上げられます。配偶者の合計所得金額が90万円を超えると控除額が所得に応じて段階的に減っていきます。
(3)配偶者控除における配偶者の所得要件(合計所得金額38万円以下)は変更ありません。
(4)納税義務者が所得制限を超過して配偶者控除が適用できない場合も、納税義務者の均等割・所得割非課税の所得の算定や、障害者控除の適用については現行どおりとなります。
お問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5640(直通)
ファクス:049-226-2540