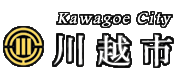ウエルシュ菌
最終更新日:2023年12月26日
ウエルシュ菌とは
ウエルシュ菌は、芽胞を形成する偏性嫌気性の細菌(酸素があると増殖できない細菌)で、ヒトや動物の腸管内、土壌、下水、食品又は塵埃等自然界に広く分布しています。
自然界に分布するウエルシュ菌は、易熱性芽胞(100℃ 数分で死滅)を形成するものが多いですが、食中毒は主に耐熱性芽胞(100℃ 1時間から6時間でも生存)を形成する菌によって引き起こされています。
※ 芽胞とは・・・細菌の中には増殖する環境が悪くなると菌体内に芽胞を作って休眠状態となるものがあります。芽胞は、熱や乾燥に強く簡単に殺菌できないので注意が必要です。芽胞は周囲の環境が適切な状態になると、再び元の形に戻り増殖を始めます。
発生機序
大量に加熱調理するとき、鍋の底では酸素が少なくなり、ウエルシュ菌の発育に好条件となります。食材にウエルシュ菌が付着していた場合ウエルシュ菌は熱に強い芽胞を作り、適温に下がったときに元の形に戻り急速に増殖します。ヒトが食物と共にウエルシュ菌を非常に多く摂取すると、一部が腸に達し、毒素が作られ下痢を起こします。
原因(媒介)食品
ウエルシュ菌食中毒の原因食品としては、カレー、シチュー、およびパーティー・旅館での複合調理食品によるものが多く、特に食肉、魚介類および野菜類を使用した煮物や大量調理食品で多くみられます。
症状
6時間から18時間(平均10時間)の潜伏期間の後、主に腹痛と下痢等の症状を起こしますが、発熱や嘔吐はほとんどみられません。ほとんどの場合、発症後1日から2日で回復するとされていますが、基礎疾患のある患者、特に子供や高齢者ではまれに重症化することが知られています。
予防方法
耐熱性芽胞は100℃で1時間から6時間の加熱に耐えると考えられています。したがって、通常の加熱調理では食品中のウエルシュ菌芽胞を死滅させることはできないと考えられます。
ウエルシュ菌は自然界の常在菌であるため、食品への汚染を根絶することは不可能ですが、発症には多くの菌量が必要とされているため、加熱殺菌と増殖防止が予防のための最も有効な手段となります。
加熱殺菌;十分に加熱することにより生残菌を少なくする。温め直すなどの再加熱、さらに中心部まで十分に熱(75℃以上)を通すことで、芽胞から元の形に戻ったウエルシュ菌を死滅させる。
増殖防止
- 調理後速やかに喫食する。
- 加熱調理品を冷却する場合、小分けして好気(酸素に接触する)状態で保存すると同時に、すばやく20℃以下に下げる。
- 食品保存は10℃以下または55℃以上で行う。
関連情報
![]() ウエルシュ菌食中毒(食品安全委員会ファクトシート)(外部サイト)
ウエルシュ菌食中毒(食品安全委員会ファクトシート)(外部サイト)
お問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103(直通)
ファクス:049-224-2261